あ~お
噫気(あいき)
噯気とも書く。おくび、いわゆるゲップのこと。
医心方(いしんぽう)
丹波康頼編纂。平安時代の永観二年(984年)に成立。全三十巻。現存する日本最古の医書。当時の中国の医書をまとめた医学全書。
⇒関連記事
噦(えつ)
「しゃっくり」のこと。
横骨(おうこつ)
恥骨のこと。または、恥骨付近にある腎経の経穴。🔗
か~こ
瘕(か)
腹腔内のしこり。形が解らないもの。
核骨(かくこつ)
足の親指の付け根の出っ張った骨(第1中足指節関節)のこと。覈骨(かくこつ)とも書く。
霍乱(かくらん)
嘔吐、下痢を伴う急性の病。酷いものは死に至る。暑い時期におきやすい。現代でいうと熱中症など。
⇒『療治之大概集』での説明
⇒『鍼灸重宝記』での説明
呵欠(かけつ)
「あくび」のこと。欠ともいう。
𩩲骬(かつう)
胸骨剣状突起のこと。または鳩尾穴の別名。🔗
岐伯(きはく・ぎはく)
中国の伝説上の医師。黄帝の侍医となり、黄帝に医術を教えたとされている。『黄帝内経』は主に黄帝と岐伯との問答形式で書かれている。
驚悸(きょうき)
強い動悸のこと。
⇒『鍼灸重宝記』での説明
欠(けつ)
「あくび」のこと。呵欠ともいう。
結喉(けっこう)
喉頭隆起(こうとうりゅうき)のこと。いわゆる喉仏(のどぼとけ)。
痃癖(げんぺき・けんびき)
首から肩の筋が張って痛むこと。現在でいう「肩こり」。
⇒『鍼灸重宝記』での説明
䯒(こう)
膝から下、下腿前面。いわゆる「すね」。䯒骨で脛骨のこと。胻も同じ。
胻(こう)
膝から下、下腿前面。いわゆる「すね」。胻骨で脛骨のこと。䯒も同じ。
黄帝(こうてい)
中国の伝説上の人物「三皇五帝」の一人。『黄帝内経』を著したとされている。黄帝の医学の師匠が岐伯とされている。
黄帝内経(こうていだいけい)
中国最古の医学書の一つ。東洋医学の原典。成立年は不明だが二千年ほど前と考えられる。『漢書』芸文志に「黄帝内経十八巻」との記載があるため、この時点では成立していたと考えられている。その後、『黄帝内経』は2つに別れたと考えられており、『素問』と『霊枢』の二つを合わせて『黄帝内経』とされている。省略して『内経』ともいわれる。
喉痺(こうひ)
のどが腫れて塞がり痛む病。酷くなると水も飲めず。声が出なくなることもある。
膕(こく・ひかがみ・よほろ)
膝の裏のくぼみ、膝窩のこと。
跟(こん)
「かかと」のこと。
跟骨(こんこつ)
「踵骨」のこと。
さ~そ
十四経発揮(じゅうしけいはっき)
元の時代の1341年に滑寿によって著された経絡経穴に関する書物。
䐐(しゅう)
膝関節のこと。
傷寒(しょうかん)
急性の熱病。腸チフスやインフルエンザ、マラリアなどが傷寒にあたるといわれる。なお現在の中国語では腸チフスを指す。
⇒『療治之大概集』での説明
⇒
傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)
張仲景により後漢の末期(西暦200年頃)に著された傷寒と雑病に関しての専門書。その当時の多くの医学書を参考につくられた。この書には今なお使われる多くの湯液(漢方薬)の処方が紹介されている。この書は、後に、傷寒に関する『傷寒論』と雑病に関する『金匱要略』に別れ、現在に伝わっている。
所生病(しょせいびょう)
是動病が進んだもの。
『難経』二十二難には「所生病とは血なり」「是動を為すことを先にし、所生を後にするなり。」と記されている。
心悸(しんき)
動悸のこと。
鍼灸甲乙経(しんきゅうこういつきょう)
『黄帝三部鍼灸甲乙経』の略。西晋の甲甫謐が編纂した中国最古の鍼灸専門書。全12巻。三世紀の後半に成立。省略して『甲乙経』とも言われる。
神農本草経(しんのうほんぞうきょう)
成立年は二千年ほど前、前漢末~後漢の中期までの間と推測されている。神農が著したことになっているが、著者不詳。中国最古の薬物学書。本草学の原典。
怔忡(せいちゅう)
持続性のひどい動悸のこと。
⇒『鍼灸重宝記』での説明
泄瀉(せっしゃ)
下痢のこと。
是動病(ぜどうびょう)
対象の経脈の乱れが起きた時に現れる症状。病の初期の状態。
『難経』二十二難には「是動とは気なり」「是動を為すことを先にし、所生を後にするなり。」と記されている。
腨(ぜん・せん・こむら)
下腿背面、腓腹部。いわゆる「ふくらはぎ」。腨腸(こむら)も同じ。
素問(そもん)
『黄帝内経素問』の略称。『霊枢』と合わせて『黄帝内経』と言われている。中国最古の医書のひとつ。成立年は不明だが2000年ほど前に成立したと考えられる。黄帝の著とされるが、著者は不詳。東洋医学の医学理論等について記載されている。
た~と
丹波 康頼(たんば の やすより)
平安時代の鍼博士。生没:延喜十二年(912年)~長徳元年(995年)。現存する日本最古の医書『医心方』を編纂したことで有名。
⇒関連記事
張 仲景(ちょう ちゅうけい)
『傷寒雑病論』を著した医師。二世紀半ばの生まれ。姓は張、名は機、字は仲景。名医として有名であった。傷寒により親族の多くが亡くなり、これに心を痛め『傷寒雑病論』を著したとされている。
腸澼(ちょうへき)
ピーピーいう下痢の事。腸癖(ちょうへき)とも書かれる。
巓(てん)
頭頂部のこと。
転筋(てんきん)
脹脛(ふくらはぎ)の痙攣。いわゆる「こむら返り」。
または、筋肉の痙攣全般を指していることもある。部位は文脈から。
な~の
難経(なんぎょう)
『黄帝八十一難経』の略称。後漢頃に著されたとの説が有力。扁鵲著とされているが実際の著者は不詳。東洋医学の重要古典の一つ。経絡治療における本治法のベースとなっている。
日腫(にっしゅ)
皮膚が化膿した腫物。
は~ほ
腓(ひ・こむら)
下腿背面、腓腹部。いわゆる「ふくらはぎ」。腓骨は現代と変わらず。
標治法(ひょうちほう)
病の症状を取り除くために局所的に行う治療。対になるのが本治法。
臏(ひん)
膝蓋骨。
蔽骨(へいこつ)
𩩲骬のこと。胸骨剣状突起。
扁鵲(へんじゃく)
中国の伝説上の名医。渤海郡鄭の人で名前は秦越人。長桑君に医術を伝授され、後に扁鵲と呼ばれるようになった。『難経』を著したとされている。『史記』扁鵲倉公列伝に記載されている。
本治法(ほんちほう)
病の症状ではなく、根本的な部分(臓腑の虚実)を治療し体全体を整える治療。対になるのが標治法。
ま~も
や~よ
善く(よく)
「よく」とよみ、「非常に」や「たびたび」といった意味。
ら~ろ
瘰癧(るいれき)
頸部の腫瘤。頸部リンパ節の結核のこと。瘰は小さいもの、癧は大きなもの。
⇒『鍼灸重宝記』での説明
霊枢(れいすう)
『黄帝内経霊枢』の略称。『素問』と合わせて『黄帝内経』と言われている。中国最古の医書のひとつ。成立年は不明だが2000年ほど前に著されたと考えられる。黄帝の著とされるが、著者は不詳。鍼灸の治療法等について記載されている。『鍼経』ともいわれる。
わ~ん
和漢三才図会(わかんさんさいずえ)
江戸時代に寺島良安によって編纂された百科事典。正徳二年(1712年)に成立。
寺島良安は医師であったため、医学関連の記述も優れている。

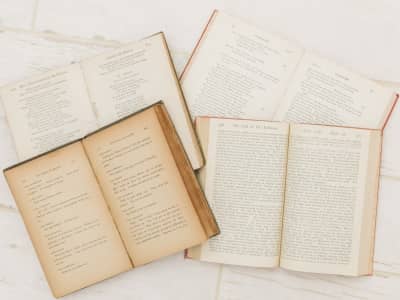


この記事へのコメント